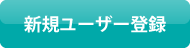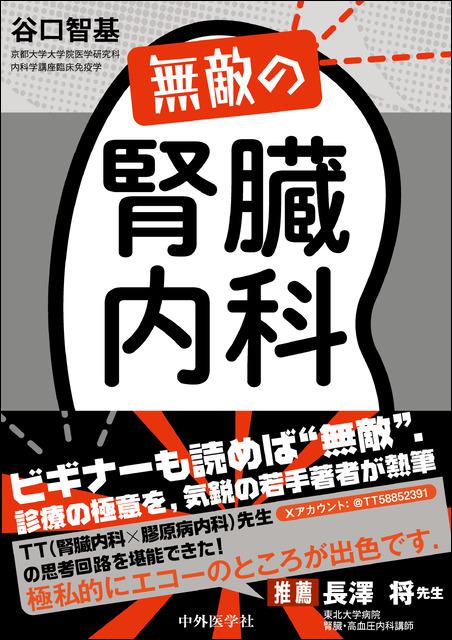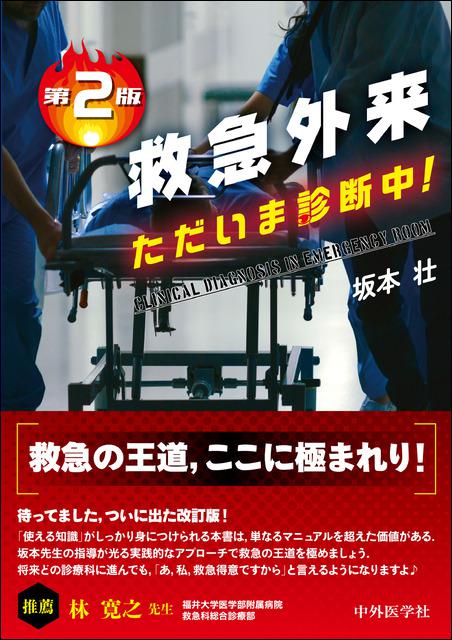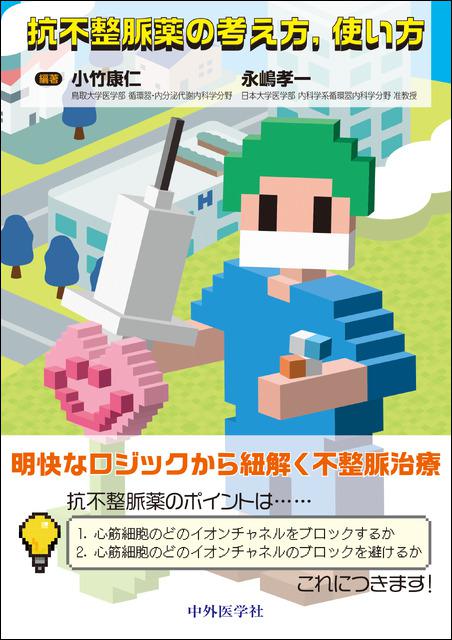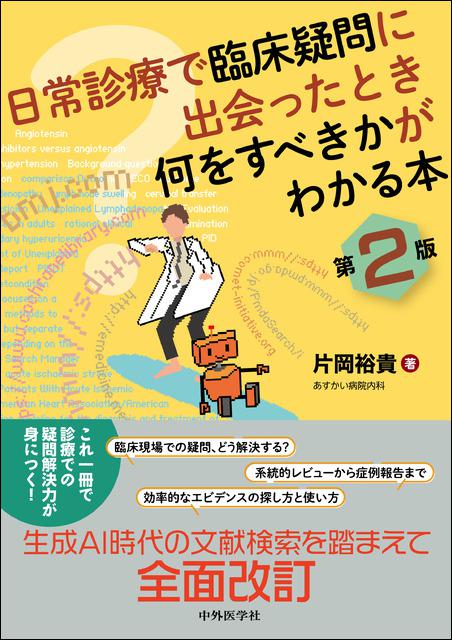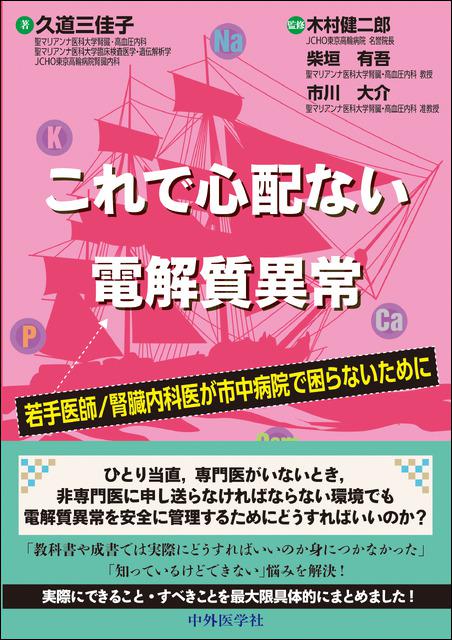Q&A医療事故調ガイドブック
一般社団法人日本医療法人協会 監修
B5判 278頁
定価5,280円(本体4,800円 + 税)
ISBN978-4-498-04832-4
2016年01月発行
在庫僅少

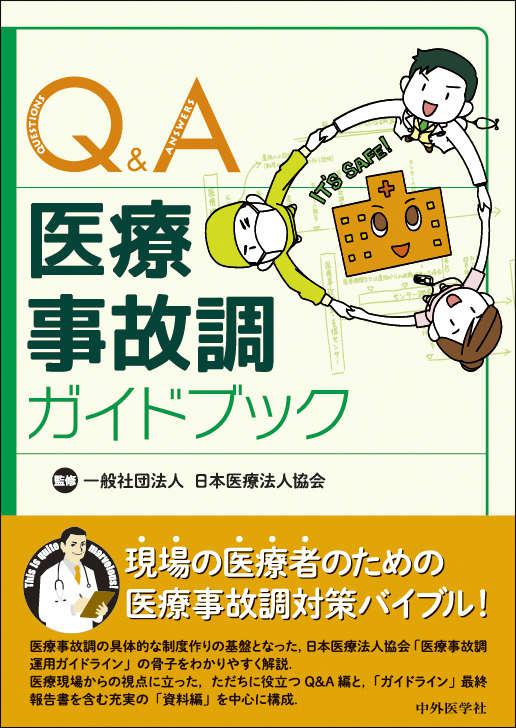
Q&A医療事故調ガイドブック
一般社団法人日本医療法人協会 監修
B5判 278頁
定価5,280円(本体4,800円 + 税)
ISBN978-4-498-04832-4
2016年01月発行
在庫僅少
医療事故の再発防止を目的として,医療事故調査制度が施行された.本書はその具体的な制度作りの基盤となった,日本医療法人協会「医療事故調運用ガイドライン」の骨子をわかりやすく解説する.医療現場でただちに役立つQ&A編と,「ガイドライン」最終報告書を含む充実の「資料編」を中心として構成.医療者のための医療事故調対策書の決定版!
はじめに
福島県立大野病院事件の医師逮捕の映像は衝撃的なものがありました.日々,忙しい中,診療に従事している医療従事者にとっては言いようもない思いがありました.これを機に一気に「医療崩壊」に突き進んだのです.この時の激震が医療界をパニックにし,正常な判断能力を麻痺させたと言えなくもありません.大野病院のショック,マスコミのヒステリックな医療バッシング,ただただ周囲からの圧力に押されるがままに,第三次試案・大綱案が作られました.
この第三次試案・大綱案は医療者の責任追及に直結する容認しがたい内容を含んでいました.第三次試案・大綱案が現場の反発を招いたのは当然の結果と言えるでしょう.医療現場からの立ち去り,リスク医療の回避,まさに「医療崩壊」の流れとなりましたが,同時に政権交代の流れにもなったのです.その後,女子医大事件,杏林割り箸事件,大野病院事件の無罪判決が出され,司法への信頼も回復に向かい,「医療崩壊」も一段落します.医療事故調問題も過去のものと皆が忘れかけていたときにも,この問題は進行し続けていたのです.医療事故調問題は誤った方向に進行していました.この流れに危機感をいだき,この問題の解決に向け先頭を走ったのが日本医療法人協会です.平成25年5月29日,厚労省は「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」を強引にとりまとめ,医療法改正に突き進みますが,医療法人協会は先頭に立って反対運動を展開,厚労省との協議を経て,大幅修正のうえ,改正医療法は公布されました.医療事故調制度は,この立法過程で,WHOドラフトガイドライン準拠の医療安全の制度としてパラダイムシフトしたのです.医療事故調制度が医療安全の制度として構築されるのとセットで,医師法21条についても,厚労省は,行政として外表異状を明示するとともに,死亡診断書記入マニュアルもこれに沿うように改訂しました.改正医療法は,妥当な内容の法律に仕上がりましたが,施行の詳細にかかわるガイドライン作りが難航します.厚労省は,「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(検討会)を組織,この検討会では,「医法協医療事故調ガイドライン」が実質的なたたき台となり,医法協案を軸に,平成27年3月20日の検討会合意に至ります.検討会合意を受け,医療法人協会は,日本医療法人協会「医療事故調運用ガイドライン」最終報告書(医法協運用ガイドライン)を公表しました.
本著書は,改正医療法,改正医療法施行規則,医政局長通知,3月20日検討会合意の基本となった医法協案に基づき,医法協運用ガイドラインの骨子をわかりやすく解説したものです.著者は,厚労省検討会構成員および医法協運用ガイドライン作成委員会メンバーです.医療現場にただちに役立つ内容となっており,本年10月の制度施行に備え,みなさまの種々の疑問点にお答えできるものと思っています.
2015年10月
小田原良治
目 次
■どうして医療事故調なんてものが出来たのか─東京都立広尾病院事件の真実─ 〈田邉 昇〉
■WHOドラフトガイドラインとは 〈佐藤一樹〉
■免責型ではないこと 〈井上清成〉
第1部 Q&A編
I.総論
Q1 今回の医療事故制度は,どのような経緯で,何を目的としてできたのでしょうか? 〈伊藤雅史〉
Q2 今回の制度はWHOドラフトガイドラインに依拠すると聞きましたが,これは出されてから10年
近くになります.今でも有効なガイドラインですか? 〈佐藤一樹〉
Q3 厚労省の検討部会でも医療法人協会の委員が多く参画し,医療法人協会のガイドラインが通知や
省令などの叩き台になったようですが,医療法人協会とはどのような団体なのですか? 〈伊藤雅史〉
Q4 どうして医療法人協会が医療事故調査制度に深く関わるようになったのですか? 〈小田原良治〉
II.医療事故調査の窓口について
Q5 医療事故であるかないかの判断を相談する窓口を探しています.どこに相談すればよいのでしょうか? 〈小田原良治〉
Q6 医療事故調査・支援センターはどのような組織ですか.信用できるのでしょうか? 〈小田原良治〉
Q7 医療事故調査・支援センターの再調査はどのような場合に行われるのでしょうか.また,それを防ぐ
ためにはどうしたらよいでしょうか? 〈小田原良治〉
III.報告の対象となる事例について
Q8 どんな事例が報告対象ですか.医療事故の定義はどうなっていますか?「医療事故」は他の制度や
書物の定義と同じでしょうか? 〈坂根みち子〉
Q9 報告対象がかなり限定されているようですが,医療事故の防止には広くセンターに報告したほうが
よいのではないでしょうか? 〈坂根みち子〉
Q10 報告の対象として「医療に起因し」,とありますが,どのような「医療」が報告対象に含まれ
ますか? 〈岡崎幸治〉
Q11 医療事故の報告の対象としないことが明らかな類型はありますか? 〈於曽能正博〉
Q12 医療に起因あるいは疑いとはどの程度の類型を言うのでしょうか? 〈小田原良治 満岡 渉〉
Q13 予期しない死亡とはどのようなものですか? 〈岡崎幸治〉
Q14 「予期した死亡」である旨を事前にカルテに記載していなかったり,患者さん自身に説明した記録が
残っていなかったりの場合でも,センター報告の対象とならない事案があると聞きました.どのよ
うな場合ですか?緊急症例以外にもありますか? 〈佐藤一樹〉
Q15 単純過誤,薬の間違いなどは報告対象ですか? 報告対象事例について,厚生労働省のホームページ
や検討会の取りまとめでは,「過誤の有無は問わない」と明記されています.一方で,省令や通知
には「過誤」という文言が見当たりません.結局,過誤が疑われる事案は報告の対象になるので
すか,ならないのですか? 〈坂根みち子〉
IV.報告対象の具体例
Q16 以下の例ごとに,報告対象になるのか,ならないのか教えて下さい. 〈田邉 昇 山崎祥光〉
V.報告の方法について
Q17 医療事故の発生報告は具体的にどのような方法で行うのでしょうか.書式等はありますか?
〈岡崎幸治〉
Q18 センターへの事例発生報告の時間的制限はありますか? 24時間は関係なくなったのですか?
〈小田原良治〉
Q19 センター報告の際に,遺族とはどのように対応するべきでしょうか.言ってはいけないことは
ありますか? 〈山崎祥光〉
VI.報告と他制度について
Q20 センターへの「報告」は,なぜ「届出」でなく「報告」なのですか? 〈佐藤一樹〉
Q21 今回の制度でセンターに報告しておけば医師法21条の届出はいらないのですね.医療事故による死亡
は異状死とは異なるのですか.異状死体と異状死は違うと書いてある本もあり,医療事故による死
亡と混乱しています. 〈佐藤一樹〉
Q22 医療事故を報告しない場合,何か罰則など,ペナルティーはありますか. 医師法21条は異状死体の届
出義務違反は罰金刑がありますが. 〈田邉 昇〉
Q23 センターへの報告以外に,医療事故があった場合に報告や届け出をする制度はありますか.医師法21
条以外にあれば教えて下さい. 〈山崎祥光〉
Q24 医師法21条では,外表異状がなければ届出の対象にならないことがよく理解できました.
では,1995年以降厚生省が診療関連死を警察に届け出るように誘導した「死亡診断書記入マニュアル」や,2000
年に厚生省国立病院部が国立病院の施設長に,医療過誤による死亡や傷害を警察に届け出るよう指導
した「リスクマネージメントマニュアル作成指針」は現在どうなりましたか? 〈満岡 渉〉
Q25 遺族から警察に届けてほしい,あるいは届け出ると言われたらどうしたらよいですか?
〈坂根みち子〉
VII.院内調査の方法について
Q26 院内調査はどのようなことを調査するのでしょうか.留意する点を教えて下さい. 〈於曽能正博〉
Q27 医療事故の院内事故調査の方法で医療安全の立場から推奨できる方法を実践している病院はどこが
ありますか? 日本の病院だけでなく,グローバルレベルの方法を教えてください.逆に真似をし
てはいけない方法があったら教えて下さい. 〈佐藤一樹〉
Q28 群馬大学腹腔鏡手術事件や東京女子医科大学プロポフォール事件,千葉県がんセンター腹腔鏡
手術事件の報告書が強く批判されているのはなぜですか? 今回の制度の院内事故調査のセン
ター報告との関連で教えて下さい. 〈佐藤一樹〉
Q29 厚生労働省ホームページのQ&A(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000061201.html)のQ3には,複数の医療機関にまたがって医療を提供した結果の死亡であった
場合,「当該患者の死亡が発生した医療機関から,搬送元となった医療機関に対して,当該患者の
死亡の事実とその状況について情報提供し,医療事故に該当するかどうかについて,両者で連携
して判断していただいた上で,原則として当該死亡の要因となった医療を提供した医療機関から
報告していただくことになります.」とありますが,搬送元医療機関からさらに遡って情報提供
してもらう必要がある場合は,どのくらい過去にまで遡らなければならないのでしょうか?
〈中島恒夫〉
Q30 院内調査を行うに当たり,自院で十分調査が行える場合であっても外部からの委員は必ず入れる
のですか? 〈中島恒夫〉
Q31 院内事故調査で収集した内部資料に,保管義務はありますか? 〈中島恒夫 田邉 昇〉
Q32 医療事故調査支援団体(以下,支援団体)とは何ですか.支援団体は,どのような業務を行うの
でしょうか.支援団体となったり,外部委員として支援要請があった場合の注意を教えて下さい.
〈満岡 渉〉
Q33 各地にできる医療事故調査等支援団体(以下,支援団体)については,「地域間における事故調
査の内容及び質の格差が生じないようにすべきだ」「事故調査は中立性,透明性及び公正性が
確保されるべきだ」という意見があります.地域間の事故調査に差があってはいけないのでしょ
うか.事故調査に中立性,透明性は重要でしょうか. 〈満岡 渉〉
VIII.院内事故調査報告について
Q34 院内事故調査報告書はどのような事項を記載するのでしょうか? 〈岡崎幸治〉
Q35 センターへの院内事故調査結果報告は,「省令」そのものでは「医療従事者が識別できないよう
加工する」旨が明記されています.一方で,該当する法律の「通知」の省令欄には,匿名化となっ
ています.どちらが正しいのですか? 省令(平成27年5月8日付の『医政発0508第1号』)では,
センターへの院内事故調査結果報告は,「当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報と
の照合による識別を含む.事項において同じ.)ができないように加工した報告書を提出しなけ
ればならない.」と明記されています.一方で,省令の別添書類では「匿名化」という用語を
多用しています.個人情報に該当する項目を単純に黒塗りにすればよいのですか?
〈中島恒夫 佐藤一樹〉
Q36 良い報告書,悪い報告書の例をそれぞれ教えて下さい. 〈大磯義一郎〉
Q37 院内事故調査の際に収集もしくは作成した内部資料などは裁判で開示対象になりますか?
〈山崎祥光〉
Q38 院内調査が終了
したら調査結果を遺族に説明することとなっていますが,なにをどの程度説明するべきでしょ
うか.また,院内事故報告書を作成する以前にその内容を遺族に見せて遺族の納得がいくよう
に書き換える必要などはあるのでしょうか? 医療安全の確保という目的に照らして教えて下さい.
〈満岡 渉〉
Q39 遺族団体には,「報告書を渡してくれれば,警察に告訴したり,被害届出を出したりしない」とか,
「民事事件にはならない」と主張している人がいます.本当でしょうか.報告書を渡しても,刑
事事件で業務上過失致死傷罪や民事事件になった事件があれば教えて下さい. 〈佐藤一樹〉
Q40 m3.comのアンケートでは実に80%以上の医師が「院内事故調査報告書を遺族に渡すべきでない」と
答えています.一方で,日本病院会のアンケートでは70%以上が「渡すべき」と答えたと会長が言っ
て,真っ向から逆の結果になっています.何故,これだけの違いが生じたのでしょうか?
〈中島恒夫〉
Q41 今回の法律の目的は医療安全の確保です.法律では,「再発防止策を院内報告に記載しなくてもよ
い」と読み取れます.では,どのような方法で医療安全の確保を行うのですか? 〈於曽能正博〉
Q42 報告書等の内容から,医療従事者の個人情報が特定された場合,医療従事者は何をしたらよいです
か?また,裁判の資料に用いられ,特定されたり,被告になりそうなそうなときはどうすれば
よいでしょうか? 〈中島恒夫〉
第2部 資料編
資料(1) 日本医療法人協会「医療事故調運用ガイドライン」最終報告書
資料(2) World Alliance For Patient Safety WHO Draft Guidelines For Adverse Event Reporting And
Learning Systems From Information To Action 患者安全のための世界同盟 有害事象の報告・
学習システムのためのWHOドラフトガイドライン─情報分析から実のある行動へ
資料(3) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(抜粋)
資料(4) 厚生労働省令第百号
資料(5) 制度概要(厚生労働省資料)
資料(6) 参議院厚労委員会 平成26年6月10日(火曜日)午前10時1分開会
資料(7) 「診療行為に関連した患者の死亡・傷害の報告」についてのガイドラインに関する安全管理委員会・
ガイドライン作成小委員会報告
資料(8) FORAMEN(東京大学医学部昭和36年卒業生 文集)私の経験した東京都立広尾病院事件
資料(9) 憲法,刑法,刑訴法,医師法など関連法律の抜粋
資料(10) 医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案
資料(11) 通知
資料(12) 厚労省Q&A
資料(13) 声明 診療行為に関連した「異状死」について
資料(14) 生命倫理ケース・スタディ 医療事故情報の警察への報告
執筆者一覧
一般社団法人日本医療法人協会 監修
田邉 昇 中村・平井・田邉法律事務所 弁護士
厚労省「医療事故調査制度の施行に係る検討会」構成員
佐藤一樹 医療法人社団いつき会ハートクリニック院長
平成26年度厚生労働省科学研究費診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究班員
井上清成 井上法律事務所 弁護士,日本医療法人協会顧問
伊藤雅史 日本医療法人協会常務理事,東京都医師会理事
小田原良治 日本医療法人協会常務理事,厚労省「医療事故調査制度の施行に係る検討会」構成員
坂根みち子 医療法人櫻坂・坂根Mクリニック院長
岡崎幸治 日本海総合病院 医師
於曽能正博 医療法人社団爽風会おその整形外科院長
満岡 渉 医療法人社団光楓会満岡内科・循環器科院長,諫早医師会副会長
山崎祥光 井上法律事務所 弁護士
中島恒夫 一般社団法人全国医師連盟代表理事
大磯義一郎 浜松医科大学医学部教授,厚労省「医療事故調査制度の施行に係る検討会」構成員
株式会社中外医学社 〒162-0805 東京都新宿区矢来町62 TEL 03-3268-2701/FAX 03-3268-2722
Copyright (C) CHUGAI-IGAKUSHA. All rights reserved.