研修医と指導医のための在宅医療教育マニュアル
浜田久之 編著 / 蘆野吉和 編著
B6変形 484頁
定価6,380円(本体5,800円 + 税)
ISBN978-4-498-12012-9
2024年07月発行
在庫あり

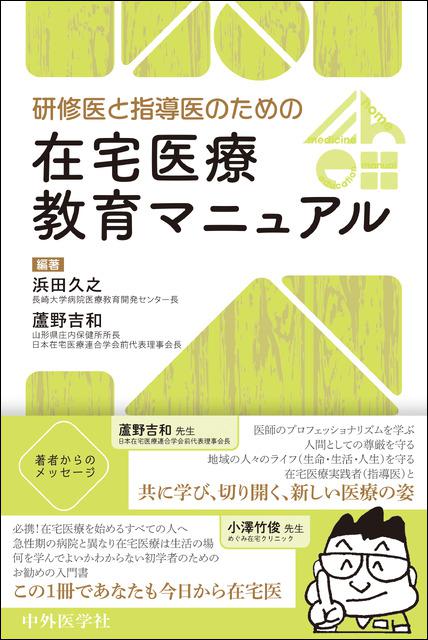
研修医と指導医のための在宅医療教育マニュアル
浜田久之 編著 / 蘆野吉和 編著
B6変形 484頁
定価6,380円(本体5,800円 + 税)
ISBN978-4-498-12012-9
2024年07月発行
在庫あり
研修医にとっても指導医にとっても待望の在宅医療マニュアル!
これから在宅医療を学ぶ研修医はもちろん,これから在宅医療を教える指導医にとっても待望の在宅医療マニュアルが完成しました.在宅医療の基本から,在宅でよく遭遇する症状別・疾患別の対応,多職種連携のコツ,さらには指導・研修方法までを網羅しました.マニュアルでの対処が難しいポイントも,各所に現れる“在宅先輩”が的確なアドバイスをしてくれます.在宅医療のやりがいや面白さを感じられる内容も盛り込み,不安だった在宅医療が“楽しみ”“得意”に変わる一冊です.
はじめに
この本を開いてくれて,ありがとうございます!
【本書のコンセプト】
1)本書の特徴
1 わかりやすく,在宅医療を医学生・研修医・若手医師へ伝える本です.
2 楽しく学べるように,在宅医療のベテランの先生方が,ガイドしてくれる本です.
3 はじめて在宅医療を行う医師や看護師などの医療者にも,理解できる本です.
4 教える立ち場の医師や看護師やコメディカルに,教える内容とポイントが示された本です.
2) 在宅医療では,今まで皆さんが,病院や診療所などで修得してきたことに加え,様々なことが必要となってきます.本書を読むと
1 在宅医療時に,必要な医療的な知識が修得できます.
2 在宅医療の時に,必須であるスキルやその習得方法について理解できます.
3 患者さん宅に伺い医療を行う際の心構えや態度や所作について学べます.
3)本書の利用の仕方
1 『在宅先輩』が,あなたを楽しくガイドします.どこからでも読めます.
2 はじめての方は,総論を読んでください.訪問時の注意点や効率的な診察の仕方がわかります.
3 各疾患については,(はじめに)を読んで,好きなところから読んでください.具体的な症例をイメージしたいときは,症例から読んでください.
4 指導医・指導者の方は,総論を読み,各疾患の<学びと教えのポイント>を熟読ください.
【在宅医療は,今後,大きな医療の柱となります】
〇在宅医療に対して,国民のニーズが高まっています!
60%以上の国民が「自宅で療養したい」と回答し,また要介護状態になっても,自宅や子供・親族の家での介護を希望する人が4割を超えています(高齢者の健康に関する意識調査 平成19年度内閣府).
→本書は,患者さんの声や視点を大事にする執筆陣で構成されています.
〇在宅医療を国は推進しています!
診療報酬では,2006年に「在宅で療養する患者のかかりつけ医機能の確立と在宅療養の推進在宅療養支援診療所の創設」,2012年に「在宅医療の充実と評価機能強化型在宅療養支援診療所・病院の創設」などで加算をし,同年医療法や予算につても「在宅医療連携拠点事業(2100百万円)」などを行っています.
→本書は,国の政策などの解説もあり,より深く理解できます.
〇在宅医療の需要は,急速に高まっています!
2025年に向け,在宅医療の需要は,「高齢化の進展」や「地域医療構想による病床の機能分化・連携」に伴い,大きく増加することが見込まれています.医療を取り巻く環境の変化と地域包括ケアシステムの中で,在宅医療を理解することが必要です(資料 在宅医療政策の方向性令和2年3月15日厚生労働省医政局地域医療計画課).
→本書は,地域包括ケアシステムの解説も行い,上記内容をより深く理解できます.
〇 在宅医療ができる医療人の育成が求められています=教える人が求められています!
医学部のコアカリキュラムの中に,「在宅医療を含む地域医療への貢献」があり,各大学で地域医療機関と一緒に様々なカリキュラムを組んでいます.医科初期研修では,2020年より研修医が経験すべき必須項目に在宅医療が入りました.すべての医師は,これから,在宅医療を経験しなくてはならなくなったのです.
看護師養成のカリキュラムの中でも,在宅看護論や在宅援助技術論,生涯広域健康看護実習(在宅看護)が入り学校が増えています.認定看護師教育課程の中にも,在宅ケア分野(看護師特定行為研修を組み込んだ課程)などがあります.
理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などのリハビリの専門職による訪問リハビリテーション,薬剤師による訪問サービスなども盛んになってきており,さらに,栄養士やケアマネージャーの育成も求められています.
つまり,在宅医療を教える人材も必要とされているのです.
→本書は,教える人にも対応しています!
【この本の成り立ち】
僕は,30歳代に,野戦病院で,10年間働きました.国立長崎中央病院という海軍病院が前身で,今は,ドクターヘリが飛ぶ立派な医療センターになっています.
当時,毎日,毎日,急患が運ばれてきて,僕達の病棟(総合診療科)に,夜間の入院が平均5名,多い時で10名ほどが,入院となりました.医師は実質2名で,当直は,毎週1回あり,ほとんど眠れませんでした.
それでも,研修医が2〜3名回ってきて,若いスタッフが多く楽しい時代でした.
毎朝7時半に,最も重要な話し合いが始まります.医局に内科の重鎮のある先生,当直明けの疲れはてた先生と僕が集まりました.タバコの吸い殻と空になった缶コーヒーが並ぶテーブル.つけっぱなしの無音のテレビと古いソファー.窓の横には,黒板があって,当直の先生がチョークを握り,その夜に入院した患者さんの名前と年齢と診断名と入院病棟を,カタカタと音を立てながら書きだします.
「お〜,今日は6人か.たいしたことないな.じゃあ,全部,浜ちゃん(僕のこと)頼むよ」と,重鎮の先生がタバコを吸いながら言いました.
「え〜,それは,いくらなんでも」と,内科医の中で一番若かった僕は,苦笑いしながら反抗しました.ひとりは,明らかに循環器だし,もうひとりは消化器だし,この人だって呼吸器でいいんじゃないか? 面倒そうな患者を全部,総合診療科に押し付けるのは納得がいかない.僕の目に炎がともろうとすると,
「まっ,君が一番若いし,若い時は勉強,勉強.さて,私は,外来に…」と,僕の肩をポンと叩いて,重鎮の先生は,「イッツ,オートマチック〜〜」と歌いながら出てゆきました.
当時,宇多田ヒカルの「Automatic」が流れ,僕は,必然的に,機械的に,自動的に,何も考えず馬車馬のように働かされていました.苦笑.
それから,僕は,南2階病棟(後に新館が立ち7B病棟)へ走ります.長い廊下を走りながら,看護婦長さんが怒る姿を想像していました.
「6人も取ったんですか! ベッドないですよ! 入れるなら出してください!」
他の病棟に入院した患者さんを自分の病棟へ移すことが,当時のその病院のルールでした.南2階病棟の患者さんを把握し,患者さんを退院させて,ベッドの空きを作ることが僕の重要任務でした.
だから,研修医の先生に,「担当患者のAさんば,そろそろ退院させんね〜. 明日くらによかね?」と,迫ったり….ある時は,患者さんに,「Bさん,突然で申し訳なかとですが,今日の午後に退院してもらえんですか?」とか,「師長さん,Cさんば,転院させよう.俺が家族に話すけん,連絡して」などなど.長崎の田舎の病院でそんなことをしていました.20年以上も前のことです.
つまり,病院のベッドをくるくる回して,回転率をあげて,患者さんを出し入れするのが仕事でした.若い僕は,様々な方に大変失礼なことを申し上げました,ごめんなさい!
かっこよく言えば,僕たちは,その地域の医療を守るため,住民の皆さんの医療ニーズにこたえるために,バタバタと働いていたわけですが,実質上は,非常に少ない医師で,40病床を維持していました.
私も含め,皆若い医師たちでしたが,まったく余裕がなく目の前のことで精いっぱいでした.入ってくる患者さんの対応に忙しく,患者さんが退院した後のことは,薬を出して,サマリーを書くのがやっとのことでした.退院後のひとりひとりの患者さんの生活など,みじんも,これっぽっちも考えていませんでした.
その後,またいろいろあり,留学を機に,私は,病棟医をやめました.
日本に帰って来てから,先輩のクリニックで,在宅医療(訪問医療)をやらせてもらうようになりました.週に2回,約30人の患者さん宅を回らせてもらいました.2007年のことです.
「こんにちは!」と,靴を脱ぎ,はじめて,患者さんの自宅にあがる.他人の家です.「内科の医者の浜田です,よろしくおねがいします」と,挨拶をして,お話を聞き,血圧を測る.ものすごくドキドキしました.きょろきょろ家の中を見回していいのか,わるいのか,どこに視線をもってゆけばいいのか….聴診器を握り,診察しました.私は,研修医のように緊張していました.
在宅医療は,私にとっては,衝撃的でした.
野戦病院で,ベッドを回し忙しさに酔いしれていた自分,中核病院で病棟医長として息巻いていた自分,研修医を引き連れていい気になっていた自分は,なんと傲慢な考え方をしていたんだろうと思いました.まったく退院後の患者さんのことを考えていませんでした.ひどく,反省しました.
病院での医療は,2時間ドラマ.
起承転結があり,だいたいの場合は,2〜3週間でドラマは終わります.
在宅での医療は,大河ドラマ.
起承転結はありますが,一般的に,延々と,淡々と続きます.時には,だらだらと.非常に退屈ですが,何も起こらない今日を明日に続ける努力が在宅医療と思います.終わりは,突然やってくることもあり,予想できません.いろいろな沢山のドラマがあります.在宅医療は,医師として,多くのことを学べる場であると思います.
2010年頃より,医学生や研修医を連れて,学びの場として,在宅医療を実践するようになりました.もう,10年以上になりますが,かなりの試行錯誤を行い,今は,一定のフォーマットを作り,短時間で在宅医療の入り口を体験する教育コンテンツを確立したと自負しております.
2020年より在宅医療を経験することが,医科臨床研修医の必須項目となりました.つまり,国は,本格的に在宅医療に従事する医療人を育てたいと思い始めたのです.これは,我々にとっては大きなチャンスと思います.
そこで,2020年に,「在宅医療教育マニュアル」をアマゾンのキンドルで無料の電子版の本として自費出版しました.驚くことに,発行した月に,300件以上のダウンロードがあり,無料本ランキングの上位に入り,1,000ダウンロード以上の実績をつくりました.
僕は思いました.みなさん,在宅医療をどう学んでいいか,どう教えていいか悩んでいるのではないか.
中外医学社も同じ思いだったようで,じゃあ,皆さんの悩みを解決できるような本を作成しよう!
と,いうことになりました.
そして,長崎で在宅医療を実践している先生方へお声をかけ,さらに,日本在宅医療連合学会の先生方へつながりました.医師だけでなく,訪問看護師の皆さん,訪問リハビリの皆さん,ケアマネージャーの皆さんや様々な職種の人の「在宅先輩」が,「在宅医療に興味を持ってもらいたい!」「在宅医療に少しでもかかわってもらいたい!」という思いが沸き上がりました.自費出版版「在宅医療教育マニュアル」をもとに,大幅に加筆と改訂を行い,本書の発行に至りました.
少々長い経緯となりましたが,以上がこの本の成り立ちです.
本の中身は,短く,シンプルな表現で,わかりやすくなっています.ぜひ,「在宅先輩」と共に,ページを開いてください.この本を通して,在宅医療に興味をもってもらえれば幸いです!
浜田久之
はじめに
この本の読み進め方
CHAPTER 1●在宅医療実践の基本をマスターする
1.総論1 準備編 〈浜田久之〉
2.総論2 問診編 〈浜田久之〉
3.診察編 〈浜田久之〉
4.診察後のカルテ記載での注意事項 〈浜田久之〉
5.感染対策編 〈田代将人〉
6.高齢者を診察するときの注意点:老年医学的視点 〈浜田久之 小出優史〉
7.高齢者を診察するときの注意点:精神医学的視点 〈松坂雄亮〉
CHAPTER 2●在宅医療でよく経験する疾患をマスターする
1.認知症 〈内田直樹〉
2.褥瘡 〈塚田邦夫〉
3.フレイルとサルコペニア 〈若林秀隆〉
4.転倒と骨折 〈西野雄一朗〉
5.肺炎(誤嚥性肺炎) 〈山梨啓友〉
6.慢性心不全 〈吉本明子 弓野 大〉
7.慢性呼吸不全 〈斉藤康洋〉
8.慢性肝不全 〈谷川 健〉
9.慢性腎臓病 〈南 香名〉
10.救急処置(誤嚥 頭部打撲 転倒) 〈高橋健介〉
11.小児難病の在宅医療 〈岡田雅彦〉
12.神経難病の在宅医療 〈立石洋平〉
CHAPTER 3●在宅医療でよく経験する症候等に対する対応の仕方を学ぶ
1.痛みへの対処法(麻薬 末期がん) 〈冨安志郎〉
2.呼吸器症状(咳 痰 呼吸困難 胸水 喘鳴)への対処方法 〈山梨啓友〉
3.消化器症状(嘔気 嘔吐 便秘 下痢)への対処方法 〈土屋淳郎〉
4.食欲不振への対処方法 〈土屋淳郎〉
5.認知症に伴う精神症状への対処方法 〈内田直樹〉
6.不眠への対応 〈内田直樹〉
7.低栄養への対処方法 〈土屋淳郎〉
8.家族の不安に対処する 〈鈴木 央〉
9.関節痛への対処方法 〈道辻 徹〉
CHAPTER 4●在宅医療の教え方(指導者向け)
1.診療所等で,医学生や研修医を受け入れの際の教育的ポイント 〈浜田久之〉
2.在宅医療で指導医が実践できること 〈中桶了太〉
3.在宅医療研修を運営する上での注意点 〈中桶了太〉
4.外部資金により研修医教育(救急 外来 在宅)を行う運営方法 〈長谷敦子 泉野浩生〉
5.在宅医療は医学教育のテキストブックだ! 〈永田康浩〉
CHAPTER 5●在宅医療の基礎知識
1.在宅医療の制度 〈小笠原貞信〉
2.在宅医療で知っておくべき多職種連携 〈小笠原貞信〉
3.ネットワークの構築について 〈白髭 豊〉
CHAPTER 6●ケーススタディー
1.在宅医療がうまくいかないケースと反省点1 〈白髭 豊〉
2.在宅医療がうまくいかないケースと反省点2 〈佐藤綾子〉
CHAPTER 7●他の職種の仕事を知る
1.ケアマネジャーの仕事 〈鷲見よしみ〉
2.訪問看護の仕事 〈宮崎郁子〉
3.訪問リハビリテーションの仕事 〈田中陽理〉
4.訪問薬剤師の仕事 〈坂本岳志〉
5.訪問歯科の仕事 〈高田 靖〉
6.訪問はり・きゅう マッサージの仕事 〈?田常雄〉
7.訪問介護員(ホームヘルパー)の仕事 〈田尻 亨〉
8.医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)の仕事 〈西出真悟〉
9.在宅訪問管理栄養士の仕事 〈依田理恵子 田中弥生〉
CHAPTER 8●在宅医療の学びを深めるために
1.医師のキャリアにおいて在宅医療をどう役立てるか 〈木村琢磨〉
2.日本在宅医療連合学会について 〈蘆野吉和〉
コラム
1)僕が在宅医を目指した理由 〈松尾誠司〉
2)施設入所中の暴言や危険行動 〈立石洋平〉
3)研修医に知ってもらいたい在宅で看取るということ 〈押渕素子〉
4)在宅医療を目指す医師は,何を勉強すればよいのか? 〈谷川 健〉
5)在宅先輩が教える在宅医療教育をはじめようとする診療所等の先生のためのQ&A 〈浜田久之〉
6)在宅先輩が教えるZ世代への教え方! 〈浜田久之〉
7)在宅先輩が教える医学生や研修医への効果的なワンポイントアドバイス 〈浜田久之〉
8)在宅医療研修を体験して 〈三ツ井吾朗〉
9)研修医に知ってもらいたい在宅医療を受ける家族の思い 〈長谷敦子〉
10)祖母が受けている在宅医療 イメージと実際の違い 〈?田滝子〉
11)在宅医療研修が研修医に与える影響と在宅医療での高齢者総合指標について 〈筋田悟史〉
12)介護福祉士の仕事 〈石本淳也〉
13)ユニバーサル・ホスピスマインド 〈小澤竹俊〉
14)大学病院と在宅医療 〈野口智聡〉
15)研修医として,在宅医療と救急の両方を通して学んだこと 〈元田 玲〉
平戸市民病院の地域医療研修
在宅先輩 〈詫摩和彦〉
執筆者一覧
浜田久之 長崎大学病院医療教育開発センター 編著
蘆野吉和 山形県庄内保健所 編著
田代将人 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床感染症学長崎大学病院感染制御教育センター
小出優史 長崎記念病院
松坂雄亮 長崎県精神医療センター
松尾誠司 長崎宝在宅医療クリニック
内田直樹 すずらん会たろうクリニック
塚田邦夫 高岡駅南クリニック
若林秀隆 東京女子医科大学病院リハビリテーション科
西野雄一朗 長崎大学病院外傷センター
山梨啓友 長崎大学病院総合診療科/感染症内科(熱研内科)
吉本明子 ゆみのハートクリニック
弓野 大 医療法人社団ゆみの
斉藤康洋 GPクリニック自由が丘
谷川 健 谷川放射線科胃腸科医院
南 香名 日浦病院腎臓内科
高橋健介 長崎大学病院高度救命救急センター救急国際医療支援室
岡田雅彦 みさかえの園あゆみの家
立石洋平 長崎大学病院脳神経内科
押渕素子 押渕医院
冨安志郎 医療法人とみやす在宅クリニック
土屋淳郎 土屋医院
鈴木 央 鈴木内科医院
道辻 徹 佐世保中央病院リウマチ膠原病センター
中桶了太 平戸市民病院
長谷敦子 長崎大学病院医療教育開発センター長崎外来医療教育室
泉野浩生 長崎大学病院医療教育開発センター長崎外来医療教育室
永田康浩 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学分野
三ツ井吾朗 神鋼記念病院脳神経内科
小笠原貞信 長崎記念病院内科
白髭 豊 白髭内科医院
佐藤綾子 かご町サトウ医院
濱田滝子 長崎大学病院研修医
筋田悟史 長崎大学病院研修医
鷲見よしみ オーク介護支援センター
宮崎郁子 訪問看護ナーシングバディ
田中陽理 長崎記念病院リハビリテーション部
坂本岳志 あけぼのファーマシーグループ在宅支援室
高田 靖 高田歯科医院
高田常雄 健康ハウス・タカダ
田尻 亨 熊本市社会福祉事業団中央ヘルパー事業所
石本淳也 リデルライトホーム
西出真悟 オレンジホームケアクリニック
依田理恵子 南大和病院栄養部
田中弥生 関東学院大学栄養学部
小澤竹俊 めぐみ在宅クリニック
木村琢磨 東京医科歯科大学介護・在宅医療連携システム開発学/総合診療科
野口智聡 長崎大学病院研修医
元田 玲 長崎大学病院研修医
株式会社中外医学社 〒162-0805 東京都新宿区矢来町62 TEL 03-3268-2701/FAX 03-3268-2722
Copyright (C) CHUGAI-IGAKUSHA. All rights reserved.


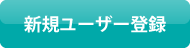
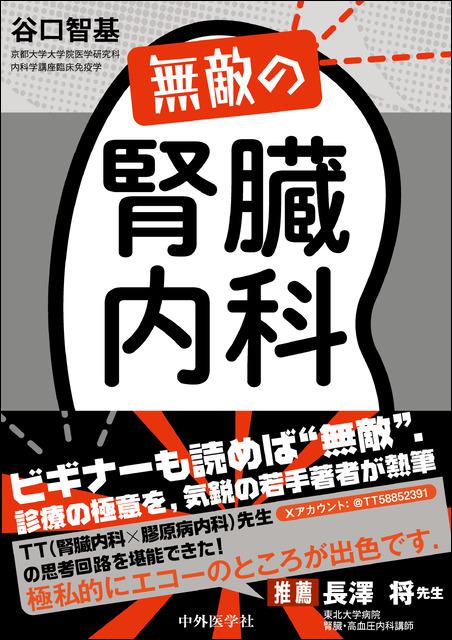
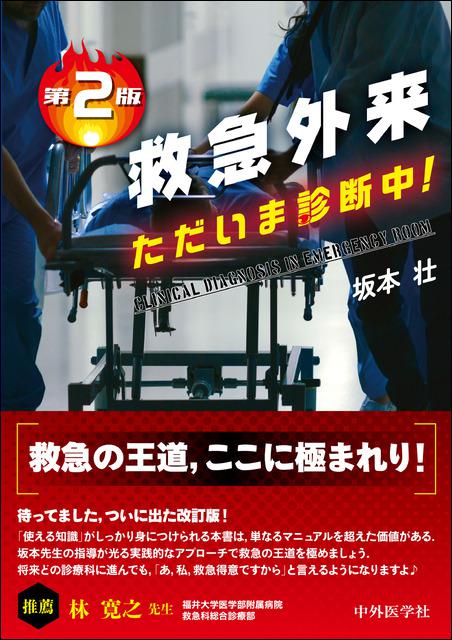
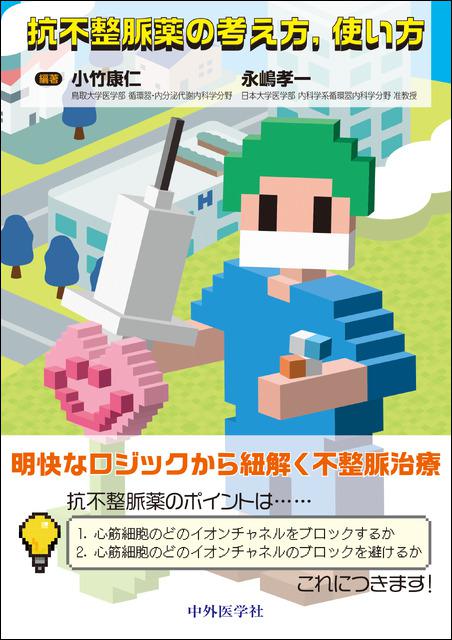
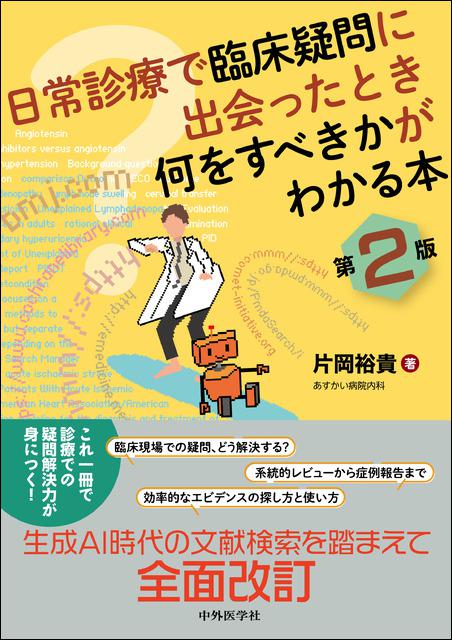
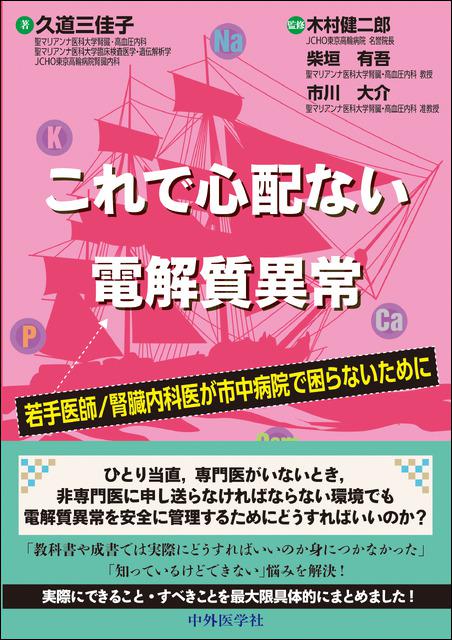
出版社からのコメント
お寄せいただきました書評をご紹介
-----------------------------------------------------------------
福井大学医学部附属病院 救急科総合診療部
林 寛之先生より
『在宅医療は人生終焉の医療でどうせ何もできない』と誤ったイメージがあり、『治療後社会復帰を目指す』先進医療とは対極にある。さらにマンパワー不足、教育不足に加えて、高度医療機器の無い丸腰の環境で戦わなければならず、いざとなったら後方病院に頭を下げて診てもらわないといけない負い目も付きまとう・・・と思いきや、否、本書はそんなネガティブなイメージを完全に払拭してくれる珠玉の書だ。我々は病気を治すんじゃない、病気を持つ人を治すんだ、いや寄り添うんだ。だって老いや病気は必ずしも治らないんだもの。患者さんを幸せにするのが医療のゴールなら、病態のフェーズが違うだけで、急性期医療も慢性期医療・在宅医療もどちらも患者さんは必要としているのだ。どっちがえらいかではなく、どっちも必要なんだ。
丸腰で戦うからこそ在宅医療ほど臨床力が試されるものはなく、知識、技術、態度、さらに経験が要求され、そんじょそこらの青二才(失礼!)がすぐ飛び込んでもうまくできるはずがない。さらに患者さんの人生を支えて伴走する中腰力と人間力が必要であり、多職種と仲良く元気にやっていく調整力も必要となる。
ある意味すごく広範囲で高度な内容を、本書は実にコンパクトにまとめてあり、医学生や研修医も在宅医療の基本から臨床実践に至るまでを体系的に学べ、在宅医療をありありとイメージしやすい構成になっているのが実に良い。
在宅医療特有の課題について包括的かつ実践的に対処法が書いてあるところがすごくいい。認知症、褥瘡、サルコペニア・フレイル、転倒・骨折、誤嚥性肺炎、〇〇不全、小児難病、神経難病、倫理問題などは在宅医療で実によく遭遇する疾患だ。各種症候に加え、せん妄、疼痛、低栄養、不眠、家族の悩みへの対応などは大きい病院ではなかなか学べない。ACPにおいてもあわてて救急車を呼ぶと検死になってしまい、家族が気まずい思いをして今までの努力にケチがつくリスクを解説している。また共に患者さんを支える多職種に対する相互理解が必要不可欠であり、各職種の視点が学べるような構成になっている。医者がお山の大将になってはいかんのだ。
在宅医療の現場に出る前の医学生や研修医には、必読の書、というより楽チンに全体像が見渡せて超お勧めの本だ。さらに指導医の心構えやZ世代の対応法まで至れり尽くせりであり、体系だった知識を伝授するうえでも指導医にも断然お勧めの書である。
-----------------------------------------------------------------
諏訪中央病院
山中克郎先生 より
ようこそ、浜ちゃんワールドへ
長崎は西洋医学発祥の地です。シーボルトが江戸時代後期(1824年)に開設した「鳴滝塾」で多くの日本人が西洋医学を学びました。長崎大学は2012年に「新・鳴滝塾」を創設し、たくさんの医学生や研修医が大学に残り研鑽を積んでいます。その立役者が浜ちゃん(浜田久之 先生)です。若い人の希望と社会ニーズをつかんで、常に新しい医学教育を実践している点が素晴らしいです。
本書はこれからますます必要とされる在宅医療の入門書です。在宅医療ほど楽しいものはありません。病院とは全く異なる患者さんの姿を訪問診療では見ることができます。初期研修医の教育としても最適です。不思議なことに、家に帰ると患者さんは元気になるのです。入院中は様々な制約がありますが、自宅では患者さんが自由に自分らしく暮らせます。入院しながら最新の医療を受けることだけが幸福なことではありません。大好きな家族に見守られながら、住み慣れた家で自由に最期まで暮らすほうが患者さんにとっては幸せかもしれません。
この本の前半では在宅医療でのCGA(高齢者総合機能評価)を意識した問診法や短時間でのルーチン診察が解説されています。老年医学的視点や精神医学的視点からの「高齢者を診察するときの注意点」は在宅医療に欠かせないポイントです。次に在宅医療でよく経験する、認知症や転倒と骨折、肺炎などの疾患について、具体的治療も含め詳しく解説されていてとても役立ちます。原因が明らかになっていない場合でも、痛みや不眠、関節痛などの症候に真摯に対応する必要があります。具体的な症例がたくさん提示されているので、個々の事例に対する診療の様子を思い描くことができます。訪問診療の現場で指導医に相談できなくても、本書の「在宅先輩の学びと教えのポイント」を読めば、ベテラン指導医から的確なアドバイスを受けることができます。
本書の後半では指導者としてどのように若手医師に在宅医療を教えればいいのかが考察されていて興味深かったです。働き方改革により医師の仕事は大きく変化しました。さらに在宅医療の制度や多職種連携について解説されています。一度は聞いたことのある用語ですが、私を含め具体的な内容を理解している人は少ないのではないでしょうか。チーム医療ではメンバーの仕事内容を理解する努力が欠かせません。職種ごとの仕事内容が詳細に述べられていて勉強になります。
いざ、素晴らしき在宅医療の世界へ。在宅医療を新たに始めようと思っているあなたに最適の書籍です。